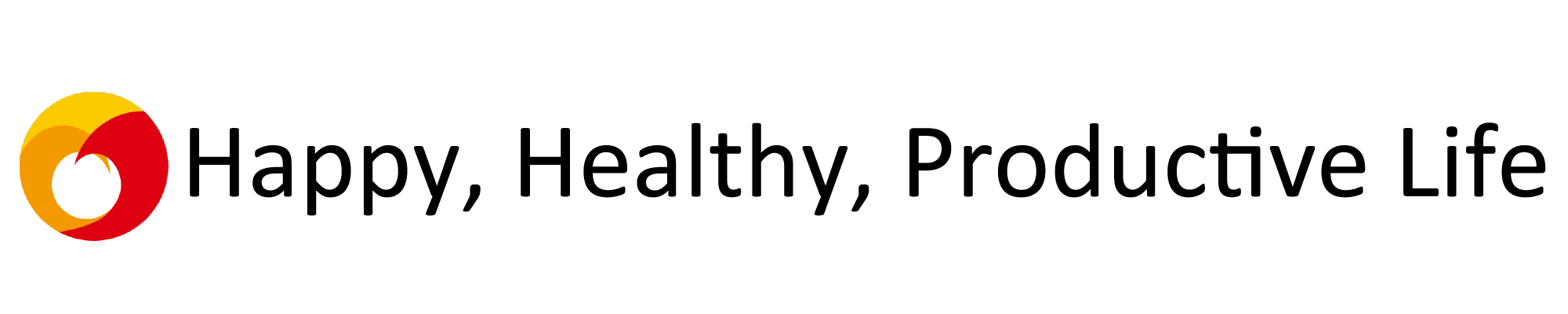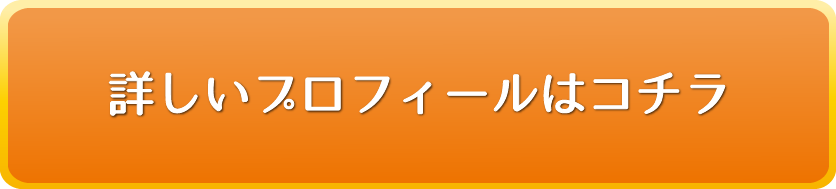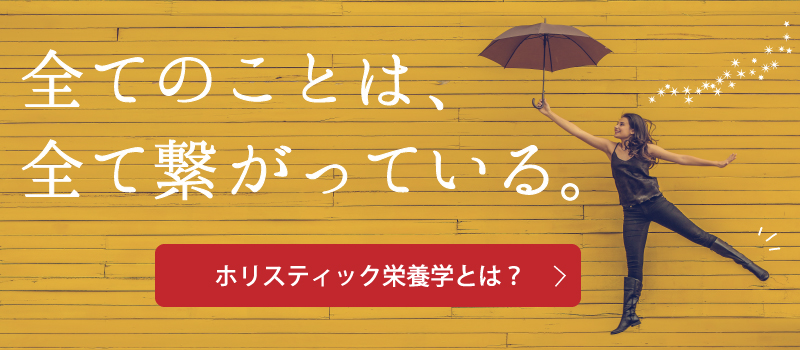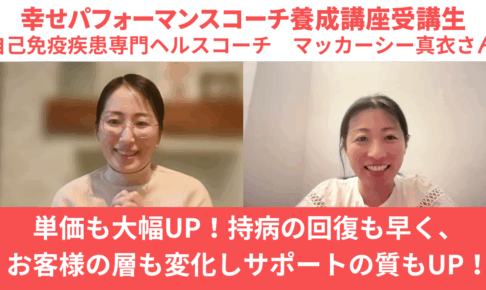コンテンツ
本日の内容はこちらの動画でも解説しています。
ホリスティック栄養学の中でもプライマリーフード(第一の栄養)とも言われる心の栄養としてとても大切にされる人間関係。その中でも、特にパートナーシップは人生で大きい影響与えますよね。
多くの人が、人間関係とかパートナーシップというと、相手との関係に視点が向きがちだけど、良いパートナーシップを築くための鍵は、実は自分自身との関係にあるって知ってましたか?
今回は、自分との関係が重要な理由と、その重要性を探ることとともに、自分との関係とも関連する、ホリスティック栄養学でもキーワードの一つとなるバイオ個性に関して、幸せになるための考え方などもお伝えします。
ちなみにホリスティック栄養学に関して、概要を知りたい人はこちらチェックしてみてくださいね♪
なぜ自分との関係が大事なのか?幸せになるための考え方
そもそも自分との関係って?
自分との関係とは、自己認識や自己理解、そして自分自身との対話のことを指します。心理学者エリクソンの自己同一性の理論では、個人が自分の存在や価値を理解し、肯定することが成熟した人間関係を築くための基盤となるとされています。具体的には、自分の過去や成長過程を受け入れ、自分の強みや弱みを理解することが重要であること。これは、他人に聞いて分かるものではなく、やはり自分に向き合い、自分がどうしたい?を自分で対話して大事にすることから得られることですよね。これにより、他者との関係でもより建設的な対話や共感が生まれやすくなります。
自分との関係の基盤、心理学者エリクソンの自己同一性の理論とは?
心理学者エリクソン(Erik Erikson)の自己同一性の理論は、人間の発達における主要な理論の一つです。エリクソンは、個人が生涯を通じて経験する発達的な課題や危機を通じて、自己同一性を確立しようとすると考えました。自己同一性とは、個人が自己の内的な一貫性や一体感を持ち、自己の存在を理解し、受容するプロセスです。
エリクソンの自己同一性の理論は以下のような特徴を持っています:
- 発達の段階性: エリクソンは生涯を通じて、8つの発達段階があると考えました。各段階では特定の発達的課題があり、それを達成することで自己同一性が形成されます。
- 危機の克服: 各段階で個人は発達的な危機(identity crisis)を経験し、その解決を試みます。例えば、幼少期の基本的信頼対不信、思春期の自己同一性対役割の拡大などがあります。
- 主要な課題と結びついた自己同一性の形成: 各段階での課題を達成することで、個人は自己同一性を強化し、自己としての一貫性や連続性を感じることができます。例えば、青年期の親密性対孤独感の課題を克服することで、自己の関係性に対する理解が深まります。
- 社会的および文化的文脈の重要性: エリクソンは、個人の自己同一性の形成には社会的および文化的な要因が重要であると述べました。特定の社会や文化の中での役割や価値観が、自己の認識や受容に影響を与えると考えました。
- 生涯発達の視点: エリクソンの理論は、生涯発達の視点から自己同一性の形成を捉えています。つまり、自己同一性は青年期や成人期だけでなく、老年期に至るまで発達し続けるプロセスであり、人生の各段階で再評価や再調整が必要な場合があるという考え方です。
エリクソンの自己同一性の理論は、心理学や教育学、臨床心理学などの分野で広く応用されています。個人の発達と成長を理解し、支援するための枠組みとして重要な役割を果たしています。
この理論でも、自分との関係を築いていくことが他の人との関係にも関連していることが分かりますね。
自分との関係が幸福感を左右する理由
自分との関係がいいということは、幸福感に直結します。自己理解と自己受容が進むと、自分の心が充実して、心にとても余裕が出てくるので、相手に対しての接し方にも余裕や優しさが生まれてきます。自己批判をしたり、相手に期待をするということも減って、まずは自分自身を大切にすることが、結果的に他人をも大切にすることに繋がるんですね。
私もこれまでのパートナーシップの中で、自分自身を大切にできていない時や、相手に期待しすぎている時、執着が起こっているときなど、自分軸ではなく、他人軸になっている時は、パートナーシップがうまくいきませんでした。
恋愛関係に入る前に、まずは自分を大事にする(自分を愛する)ことがなぜ大事なの?
自分自身をまず大事にする(愛する)ことができないと、どうなるか?
恋愛関係において、もし自分自身を愛していなければ、相手が例えば仕事でなにか嫌なことがあって家に帰ってきた、という場合、どうなるでしょうか?
自己嫌悪感がある人は、相手に嫌なことが起こっているということをすぐに自分のせいだと思い込み、機嫌を損ねたり、相手に逆に当たってしまうこともあるかもしれません。もしくは、悲しくなり、引きこもってしまうかもしれません。どちらにしても、これは、恋愛関係にとってとっても有害ですよね。結果として、お互いのコミュニケーションに溝ができてしまいますよね。
自己嫌悪感を抱いている人は、自分への自己愛は空っぽで、相手が愛を満たしてくれないことに不快感を覚えてしまうからです。自分でなんとかしようとする前に、相手へなんとかしてもらおうとする。
こう考えてみてください。自分を嫌ったり、判断したりすると、愛情は空の穴のようになりますよね。いつも「私はひどい、醜い、意地悪」などとなります。全然自分への愛がないですね。
一方、自分を愛していると、いつも愛に満ちていて、穴はありません。だから、同じ状況でも、相手が仕事で嫌なことが起こったような時でも、自分はそれを個人的に受け取ることはしません。自分は単に「相手には今日は嫌なことがあったんだなあ」と理解するだけです。これにより、自分の感情への影響はないし、口論になったりすることも起こりません。
私たちの心の世界全体は、内なる感情の状態を基盤として始まります。その基盤に自己愛がしっかり満たされている場合、愛を見つけたり感じ取ることをはるかにしやすくなります。自己嫌悪であれば、嫌悪感が常にデフォルトとしてある、ということになりますよね。
だからこそ、誰かとの関係を築く前に(もしくは築いている間でも)、まずは自分を大事にする(自分を愛する)ことってとっても大事なんですね。
夫と出会う直前に気づいた自分との関係の大切さ
夫と出会う前、実は私は11年間、未婚のシングルマザーでした。
シングルマザーの時は、私は恋愛も結婚も、もう自分の人生には無縁のものだと思いこんでいました。
「これまで出会った相手が悪かった」
「私は気が強いから、男の人は私のことを、1人で行きていけるだろうと思うに違いない」
「自分は変わった人間だから、多分私に合う人はいないだろう」
こんな「他人軸」な思い込みをずっと持っていました。
未婚で出産した時に、母親にも、「もう美咲のウェディングドレスを見ることはないかもね」と言われた、そのことも、自分の中では、「母にそう言われたから」とまた人のせいにする他人軸で、結婚はおろか、恋愛さえもできないだろうと思いこんでいたんです。
だけど、夫と出会う直前に、私は、私のことに集中していました。
会社をやめ、好きなことで思い切って起業し、「自分」の人生を楽しんでいたんです。
あの時の私は、それまでの私の人生の中で一番、自分を信頼し、自分を許して、自分へのチャレンジもしていた時でした。
誰から何を言われようが、自分のことは自分で決める、周りから見ると少し頑固に見えるくらい、私は私の軸で生きていました。
そんな時に、夫と出会ったのです。
自分でも驚いたことに、それまでのパートナーシップでは、私は相手に合わせるばかりで自己犠牲が多かったのが、夫と出会ってから、自分を一番に大事にして、自分がやると決めたこと、やりたいことは、相手に合わせるよりも、自分がどうやったらできるか?を考えて自分の人生は自分で決めることができていたんです(これは今でも続いています)。
これが、やっと私が良いパートナーシップを築けて結婚までできた理由の一つかもしれません。
もちろん、夫が理解力のある人だ、というふうにも言えるかもしれませんが、私は自分の決断のすべてを夫に話して理解してもらう、というよりも、話すこと、話さないことも自分と対話して決めて、同じ家族でも、「自分」と「他人」の関係の前に、「自分」との関係を大事にしています。
相手のことを自分はコントロールすることはできません。ネガティブな話かもしれませんが、信頼している相手であったとしても、ふと自分の前からいなくなる、ということもあるかもしれません。
そうなった時に、「あの人がいたから幸せだった」という考えだと、自分で自分を幸せにする力がない、ということにもなりますもんね。
ホリスティック栄養学の観点から見る自分との関係
実は、夫と出会う前に、私はホリスティック栄養学に出会っていました。
ホリスティック栄養学の中では、「バイオ個性」というキーワードがあります。バイオ個性というのは、人は一人ひとり違っていてすべての人に合う食べ物や生き方はないということ。
この考えを私は先に知っていたことで、「自分」に向き合い、自分との関係を大事にすることを実践していたということも大きかったです。
また、ホリスティック栄養学の考えである、食の栄養学だけでなく、環境や人間関係、精神、運動、創造性など、健康や幸せに関する背景すべてのことをバランスよく整えることで、自分と周りを包括的に見ることができ、自分との関係も自然と良くなります。
何か特定の考えに固執したり、ジャッジすることなく、物事をより包括的に、広い視点で見ることができるようになり、自分に合うものを自分で見つけ、バランスの取れた食事や適度な運動、瞑想なども含めて、自分の心と体の健康を改善していく、ということが自分との関係をよくすることにも繋がっています。
自分との関係がパートナーシップに与える影響
パートナーシップにおいて、自分との関係がどのように影響を及ぼすかについて考えてみましょう。自分自身との関係が良好であれば、他者との関係も自然と豊かになり、逆に自己認識が欠如していると、人間関係においてさまざまな困難が生じることがあります。ここでは、自分との関係がどのようにパートナーシップに影響を与えるのか、具体的な観点から掘り下げてみたいと思います。
1. 自己認識の高さとコミュニケーションの質
自己認識とは、自分自身の感情、考え方、行動パターンを理解し、それらが他者にどう影響を与えるかを認識することです。自己認識が高い人は、パートナーとのコミュニケーションにおいても次のような利点があります。
- 共感力の向上: 自己認識が高いと、自分の感情に気づきやすくなり、同時にパートナーの感情にも敏感になります。これにより、相手の立場に立って物事を考えることができ、共感的なコミュニケーションが可能になります。
- 健全な対話: 自分の気持ちやニーズを正直に表現することができるため、パートナーと健全で建設的な対話ができるようになります。これにより、誤解や摩擦を未然に防ぎ、問題解決に向けた協力的なアプローチが可能です。
2. 自己受容と関係性の安定
自己受容とは、自分の長所も短所も含めて自分をありのままに受け入れることです。自己受容ができている人は、以下のようなポジティブな影響をパートナーシップに与えます。
- 安心感と信頼感: 自分を受け入れることで、他者に対しても寛容で理解を示すことができるようになります。これにより、パートナーシップにおいてもお互いを尊重し、信頼関係を築くことが容易になります。
- 感情の安定: 自己受容ができている人は、自分の感情を適切に処理し、コントロールする力が強くなります。これにより、パートナーに対して感情的に過剰に反応することが少なくなり、関係性が安定しやすくなります。
3. 自己否定とパートナーシップのリスク
一方、自己否定的な態度は、パートナーシップにとって多くのリスクを伴います。自己否定が強いと、次のような問題が発生することが多いです。
- ネガティブな投影: 自分に対して否定的な感情を持つと、それをパートナーに投影してしまいがちです。例えば、自分に自信がないと、パートナーが自分を尊重していないと感じたり、不必要に嫉妬心を抱いたりします。
- 依存的な関係: 自己肯定感が低いと、自己の幸福や満足感をパートナーに依存しがちです。これにより、パートナーに過度な期待を抱き、関係性に不安定さが生じることがあります。
4. 自己成長とパートナーシップの発展
自己成長を重視する人は、パートナーシップにおいても次のようなポジティブな影響を与えます。
- 相互成長: 自己成長を目指す姿勢は、パートナーにも良い影響を与え、共に成長する関係を築くことができます。お互いに励まし合い、新たな目標に向かって努力することで、関係性が深化します。
- 長期的な視点: 自己成長を重視する人は、短期的な満足よりも長期的な幸福を重視します。これにより、パートナーシップも持続可能で健全なものになります。
5. 実際の事例と研究から学ぶ
心理学の研究によると、自己認識や自己受容が高い人ほど、パートナーシップにおいて高い満足度を得ていることが示されています。たとえば、Neff & Beretvas (2011) が行った、The Role of Self-compassion in Romantic Relationships(ロマンチックな関係における自己慈愛の役割)の研究では、自己慈愛(self-compassion)が高い人は、ロマンチックな関係においても相手に対して寛容であり、関係の質が高いことが示されています。このように、自己との関係がいかにパートナーシップに重要な役割を果たしているかを理解することが、より良い人間関係を築くための第一歩となります。
パートナーシップ、人生全体においても幸せになるための考え方
例えば、「夫が優しいから私は幸せ」こういう考え方を持っていると、確かにそれも幸せの一つの考え方かもしれませんが、じゃあ、夫が優しくなかったら幸せじゃないのか?ということにもなりますよね。
こういった例はよくあります。
普段優しい夫が、自分とは関係ないところのストレスで(例えば仕事でのストレス)、機嫌が悪く、家族に当たっていたとします。
自分との関係がいい人は、こんな時にしっかりと、自分と夫との境界線をもって考えることができます。
自分が悪いと思うこともないので、自分が夫の感情に影響されるようなこともなく、自分の心は余裕がある状態。夫には夫の何か問題があるのだということに気づいたら、夫のことを気遣う余裕さえも出てきます。(これは実際は、自分でも難しいなぁと感じる時はありますけどね)
だけども、パートナーシップ、人生全体においても、幸せになるための考え方としては、いつもやはり、自分で自分を幸せにできる、ということ。だから、その幸せは、相手に委ねるものではないのです。そう考えると、パートナーシップにとって、自分との関係がやっぱり大事ということは、明らかですよね。
まとめ
パートナーシップを築く上で、自分との関係を良好に保つことは、1人の時でも2人の時でもとっても大事。自己理解と自己受容を深め、ホリスティックな心と体のアプローチを取り入れることで、より豊かな人間関係を築くことができます。
自分の心と体の健康を保って幸せでいることは、自然と相手にも幸せを広げていくことに繋がっていきますね。私はこれをハッピーサークルともよんでます。これってパートナーシップだけではなく、その周りの人との人間関係にも自然と広がっていくんです♪
参考:
Erik Erikson’s Stages Of Psychosocial Development https://www.simplypsychology.org/erik-erikson.html
Neff, K. D., & Beretvas, S. N. . The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 78-98. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298868.2011.639548
☆☆☆☆☆
私が卒業した世界最大のホリスティック栄養学校、
ホリスティックヘルスコーチ資格に関しては下のリンクに詳細記載しています。
卒業生の私からの紹介で割引が最大になる大幅割引も受けることができます。
ご質問、ご相談もお気軽にこちらからお問い合わせください。
ホリスティック栄養学に関しては、こちらの記事と動画も参考にしてください。
幸せパフォーマンスコーチ養成講座の中では、ホリスティック栄養学の考えを元に、あなた自身のセルフコーチング、コーチング、栄養指導、お仕事、起業・ビジネスのヒントも細かく学べます。
年に2回の募集ですが、募集時期にはメール講座でご案内していますので、下記のメール講座にご登録くださいね。メール講座では、ホリスティック栄養学のこと、セルフコーチング、コーチング、ビジネスのこと、無料で学べます!
ご相談やご質問はこちらのお問合せフォームからも受け付けています。お気軽にお問合せください。
☆☆☆☆☆☆☆☆
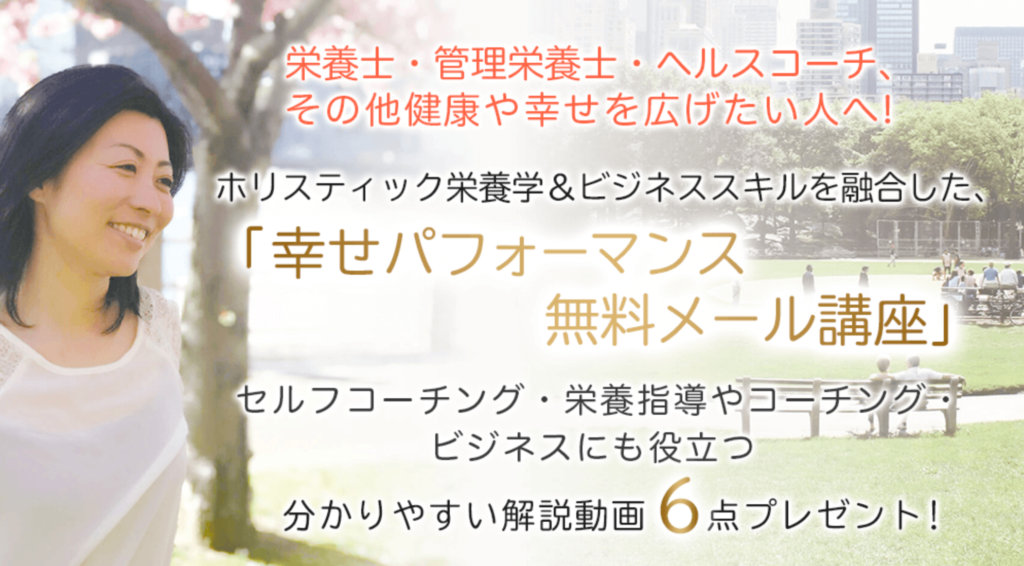
ホリスティック栄養学の考えを元に セルフコーチング・栄養指導やコーチング・ビジネスにも役立つ 「幸せパフォーマンス無料メール講座」
分かりやすい解説動画6点プレゼント!
管理栄養士・ヘルスコーチの資格を生かした仕事で起業したい人、
その他、健康や幸せを広げるお仕事をしたい人、
心 と体の一生モノのセルフコーチングに活かしたい方にオススメです。